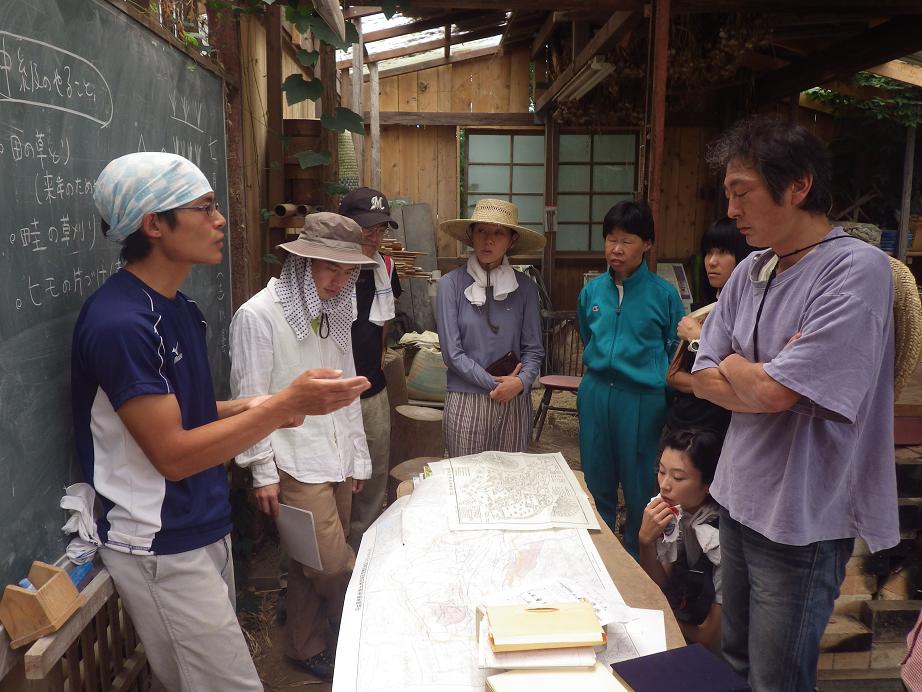~自分で食べるお米を自分で育ててみませんか?~
この講座では、大型機械などは使わずに、無農薬栽培するための、ひとつの方法を学びます。すべての田んぼに通用する万能の技術、というものはありません。いろいろな状況に応じて対応しうる見方、考え方、そして何より稲作が生活の一部になることの素晴らしさをお伝えし、田んぼを自力でやっていくのに必要なことをおさえます。
≫ 家庭稲作講座 導入編 ≫ 家庭稲作講座 応用編
家庭稲作教育ファーム 導入編 (申し込み終了)
【期間】 2014年4月~12月(計10回)
【主催】 NPO法人雨読晴耕村舎 後援:羽生市
【場所】
雨読晴耕村舎と近くの田んぼ
〒348-0065 埼玉県羽生市藤井下組666(ページ末尾参照)
【交通】
(電車)東武伊勢崎線 羽生駅 (徒歩40分、タクシー10分)
(車)東北自動車道 羽生インターから5分 (いずみ保育園近く)
【参加費】 30,000円(保険代を含む)
【募集人数】 10名(先着順)
【修了証】 羽生市農政課より修了証が発行されます(8回以上参加の方)
【備考】
・ 初めての方、女性も大歓迎です。お気軽にご参加下さい。
・ 長靴や雨具、軍手、着替えなどをご用意ください(雨天でも実施します)。
・ 昼食(パンやスープ)やお茶(お菓子)を1日700円でご提供します。
・ 2年目以降は、自分でお米を育てるコースもあります。
・ 収穫したお米(2kg)と玄米餅を差し上げます。
【申し込み】
名前・住所・携帯電話番号・メールアドレス・受講動機をご記入の上、
下記のメール宛にお送りください。
【お問い合わせ】
興味のある方は直接事務局までメールでお問い合わせください。
メールアドレス: info[at]udokuseikou.org ※[at]を@にご変更ください
■ 2014年度 スケジュール
| 日時 | 講義 | 田んぼの作業予定 | |
| 第1回 | 4月26日(土)10時~16時 | ・オリエンテーション(年間スケジュール、レンゲ不耕起栽培の特徴) ・田んぼの観察 |
・田んぼを整える (畦の整備や水路の補修など) |
| 第2回 | 5月3日(土)10時~16時 | ・稲の種類 それぞれの性格と選ぶポイント ・育苗のポイント |
・種の準備(ノゲとり、塩水選、浸種) ・種まき |
| 第3回 | 5月24日(土)10時~16時 | ・苗の成長の観察 ・カバープランツの役割、種類 |
・畔草刈り、カバープランツの植え付け ・畔塗り ・育苗(プールに入水) |
| 第4回 | 6月7日(土)10時~16時 | ・耕さない田んぼ ・田植えのポイント |
・田植え |
| 第5回 | 6月21日(土)10時~16時 | ・水管理のポイント ・田の草の種類とそれぞれの特徴 ・田んぼの生き物の観察 |
・田の草とり ・欠株の補植 ・畦の草刈り |
| 第6回 | 7月19日(土)10時~16時 | ・田の草の観察 ・田んぼ生き物の観察 |
・田の草とり ・畦の草刈り ・畦豆の植え付け |
| 第7回 | 8月30日(土)10時~16時 | ・出穂の観察 | ・畔の草刈り |
| 第8回 | 10月11日(土)10時~16時 | ・種とりの方法 ・収量の調査 |
・稲刈り、天日干し ・緑肥の種まき |
| 第9回 | 11月1日(土)10時~16時 | ・お米の上手な貯蔵方法 ・稲の副産物を活かす(ワラや籾殻、米ぬかの利用方法) ・来年のお米作りに向けて |
・脱穀、籾摺り、精米 ・ワラの片付け |
| 第10回 | 12月6日(土)10時~16時 | ・まとめ ・修了式 |
・収穫祭 (餅つき、注連飾りづくり) |
※生育状況により、開催日が1週間程度前後することがありますので、ご了承下さい。
※場所の詳細
家庭稲作講座 応用編
【場所】 雨読晴耕村舎(羽生市大字藤井下組666-1)
【定員】 10名(先着順)
【受講条件】 家庭稲作教育ファーム講座(導入編)を修了した方のみ
【参加費】 15,000円(1畝(面積約100m2)) ※空き状況に応じて2畝まで可能
【お申し込み】
名前・住所・携帯電話番号・メールアドレス・受講動機をご記入の上、
NPO法人雨読晴耕村舎 info[アットマーク]udokuseikou.org までご連絡下さい。
[アットマーク]を@にご変更ください。
【備考】
・ 講座日以外でも土曜日であれば、原則として自由に来て作業可能です。
・ 各自現地へお越しください。羽生市の貸し自転車もご利用下さい(台数に限りあり)。
・ 道具の貸し出しの他、種籾(イセヒカリ、サリークイーン、餅米、黒米)をご提供します。
・ 昼食(パンやスープ)やお茶(お菓子)を1日700円でご提供します。
・ 収量は約80kgを想定していますが、天候や品種により変動します(保証はしておりません)。
■ 2014年度 スケジュール
| 日時 | 田んぼの作業予定 | |
| 第1回 | 4月26日(土)10時~16時 | ・ 田んぼの区画分け ・ 田んぼを整える(畔の整備や水路の補修など) |
| 第2回 | 5月3日(土)10時~16時 | ・ 種の準備(ノゲとり、塩水選、浸種) ・ 種まき |
| 第3回 | 5月24日(土)10時~16時 | ・ 畔草刈り、カバープランツの植え付け ・ 畔塗り ・ 育苗(プールに入水) |
| 第4回 | 6月7日(土)10時~16時 | ・ 田植え |
| 第5回 | 6月21日(土)10時~16時 | ・ 田の草とり ・ 欠株の捕植 ・ 畔の草刈り |
| 第6回 | 7月19日(土)10時~16時 | ・ 田の草とり ・ 畔の草刈り ・ 畔豆の植え付け |
| 第7回 | 8月30日(土)10時~16時 | ・ 畔の草刈り |
| 第8回 | 10月11日(土)10時~16時
※生育状況に応じて変更あり |
・ 稲刈り、天日干し ・ 緑肥の種まき |
| 第9回 | 11月1日(土)10時~16時
※生育状況に応じて変更あり |
・ 脱穀、籾摺り、精米 ・ ワラの片付け |
| 第10回 | 12月6日(土)9時~16時 | ・ 収穫祭(餅つき、注連飾りづくり) |