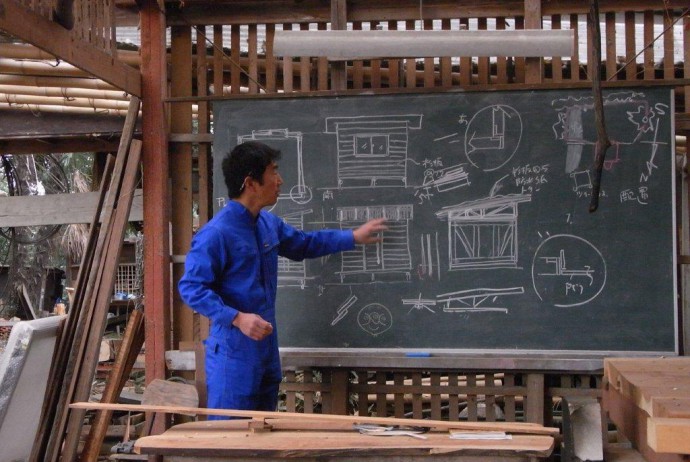昨日は小雨がときどき降る中、家庭稲作講座の最終回。
稲藁での〆縄飾りづくり実習。
羽生市による終了証の授与。
昼食はきねと臼で餅を搗き食べる。
キャロットポタージュもつくって出してみた。
継続して来シーズンも受講されるかたが多くより内容を深めていければ、と強く思った。
気象キャスターネットワークと雨読晴耕村舎の共同企画
「羽生 空と畑の環境教室」の第3回
今回も2本たてのテーマ
①屋敷林の動植物マップづくり(埼玉県生態系保護協会主任研究員の佐々木隆馬氏)
講座が始まる前にケンタと佐々木さんが雨読晴耕村舎の森を歩いた。動植物を観察する視点で眺めると森の中は輝きに満ちている。この枯れ枝の穴は何だと思います?
コゲラ(小型のキツツキ)がカミキリムシの幼虫を捕食するためにあけたもの。
佐々木さんの講座は子供たちにアクションと観察をさせてそれを解説する、というスタイルで大人も一緒に熱中してしまいました。
これはある香りの強い落ち葉を子供たちに渡し、その木をさがして地図にプロットさせたうえでその木(クスノキ)の解説をするプログラム。こういったスタイルでバッタ、蝶、爬虫類両生類などを捕獲しつつ地図上にプロットしていきました。
糧工房で久美ちゃんが準備してくれたニンジンたっぷりの昼食を食べて
午後はもうひとつのテーマ
②レンゲ・スズメのテッポウ不耕起田の稲刈り(NPO法人雨読晴耕村舎理事の谷川拓也氏)
春にこの講座で田植えをしたレンゲ・スズメのテッポウ不耕起田の稲刈りだ。田の面には稲の下にもうレンゲやスズメのテッポウ、スカシタゴボウなどが発芽して覆っている。この田んぼのサイクルについて谷川君から解説があり作業スタート。稲ははざかけして乾燥に入りました。あと2週間もしたら脱穀します。これはもち米なのでまた子供たちと餅搗きをしようね。
土曜日は久しぶりの家庭稲作講座
8月にはいってからは田んぼの作業は畦草を刈り少し中の草を抜く程度でほとんどやることが
なかった。稲の穂が出て花が咲きはじめたのでそろそろ作業再開というわけだ。
8月は私は、といえば図鑑を畦に広げて畦草を刈りながら雑草の同定をしていた。
名前やその性質を読み、覚え、また生えている状態をよく観察していくにつれこの世界にも
魅かれていく。今年は身近な動植物の世界の扉を一気に開いた感じだ。なんと世界は
生命が満ち溢れているのだろう。そして私たちの知の世界はそのひとつひとつにスポットライトを
すでにあてている。知ろうとおもう気持ちさえあればわくわくするような視点がたくさんある。
講座ではその一端を紹介した。
気象キャスターネットワークとの協同企画、親子環境学習
今回は田んぼの生き物観察
講師は三森典彰さん。田んぼに生息する動植物に関して広範な知識と
情熱で一気に子供も大人も生物の世界へ。
今年からはじめた北側の田んぼ。
雨読晴耕村舎の森のかげになる場所で田んぼとしては影の薄い存在だった。
ただ実際に作業していると生物の種類と量が多い印象をうけていた。
今日の講座で田んぼの生物たちにとっての森の存在の大きさを改めて知った。
実際にたくさん飛んでいたシノメトンボなどは育つ過程で森を利用しているそうだ。
やごの抜け殻を採取したマルタンヤンマ、イチョウウキゴケなど貴重な生物の
種が森とその緑陰によって守られてきたようだ。
マルタンヤンマについて
http://tombozukan.net/zukanyanma.htm